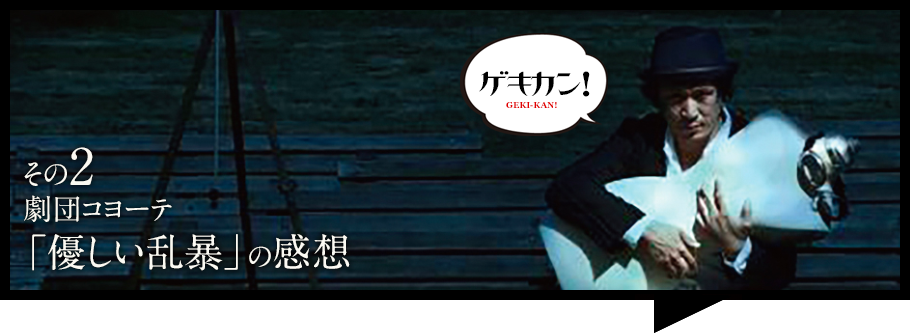
息を吸うように酒を飲み、捉えようとするほどに逃げていく、もどしかしくも心地よいリズミカルな言葉の応酬。
これは現実なのか、それとも人の心が見せる景色なのか。
「札幌演劇シーズン2021 冬」は、毒とユーモアに満ちた愛の物語でその幕を開けた。
光を抑えた舞台の上に、そろりと浮かぶバスの車内。
手前には古びたバス停があり、年季の入った青色のベンチが佇んでいる。
シンとした空気の中で、横尾寛さん演じる蟹江鳥生がゆらゆらと進み、浮かんでは消えるような語りと共に物語ははじまる。バスの車内には男と女がいて、交わされる会話は成立しているようで、していないような支離滅裂さ。
酩酊状態で船に揺られているような感覚が、なぜだかとても気持ちが良い。
物語の鍵となる人物は、脇田唯さん演じる原田摂子という名の85歳の女の子だ。
青いベンチに腰を下ろしてバスを待つその姿は、ふいに老女に戻ったり、けれど澄んだ目をした女の子だったりする。深い青の星空がよく似合い、気の遠くなるほどの長い時間を心の中に少女を留めながら過ごしてきた人なのだ、と思う。85歳の女の子の存在は、憧れであり、救いであり、救いたくなる人だ。脇田さん演じる85歳の女の子に、私はすっかり惹き込まれてしまった。
タンスのこやしを買い増やす老女や、詩人ランボーに魅せられたとぼけた殺し屋とそれを受け入れる彼女など、ふいに現れる登場人物たちもまた、みんな滑稽だったり、ユニークだったり、悲しかったり。
観ている私は、時に自分と重ねて目を逸らしたり、よく知る人に照らし合わせてみたりする。 「優しい乱暴」という作品は、観る側にそうやって委ねてくれる。
そして、誰かと語り合いたくなる。「みんなはどう観たのだろう?」と考える瞬間は、とても幸せだ。
シンガーソングライター・矢野絢子さんのミニライヴで物語の幕は下りる。
「優しい乱暴」が生まれるきっかけになったという「八十五歳の女の子」を含む心に迫るセットリストは、この劇場体験をより幸福なものとして締め括ってくれた。「優しい乱暴」の大切なラストページだ。
事前にiTuneで「八十五歳の女の子」をダウンロードしていた私。終演後、迷わず物販の列に並び、少し前の作品だという『ミチスガラ』というアルバムを購入した。演劇と音楽による久しぶりのライヴ感。今夜ゆっくり聴いてみようと、ジャケットを眺めるこの瞬間が、私はとてもうれしい。
本編が終わったあと、さらに付け足しがある作品は好きじゃない。
トークとか音楽とか、なんであれ余計に感じてしまう。作品だけで勝負してほしい。あの余韻だけを抱えて劇場をあとにしたい。いつも思う。
ところが劇団コヨーテ『優しい乱暴』。本編のあとに矢野絢子ミニライブが30分あるが、絶対に必要な30分だった。付け足しなんかじゃない、余計でもない、本編のよさを引きあげ、余韻を深く長く味あわせてくれてる最高のライブだった。
このライブをふくめての計1時間40分が、『優しい乱暴』という公演だと言っていい。なので劇団&劇場の誘導も、「本編のあとにミニライブがあります」ではなく、「本公演はこのあとミニライブに移りますのでしばらくお待ちを」という形にした方がいい。
『優しい乱暴』は亀井健の美しい言葉によるやや難解な戯曲だ。途中までは、遙か遠い星では宝石のように価値あるものだけど、地球ではなにに使うかわからないパーツたちのように思える。ひとつひとつは独特の美しさがあるのだけど、組み合わせがわからない。はたしてこのパーツはなんなんだろう? なんの意味が? と迷子になる。それらのパーツがラストに突如として噛みあって動きだし、ひとつの感動を生みだすのだけど、それでもなお、使えたのかわからない不可解なパーツも残りつづける。
そのあとに、矢野絢子のミニライブがはじまる。そこで歌われる『八十五歳の女の子』という曲こそが、『優しい乱暴』の発祥なのだという。聴いてみると一目瞭然だ(目じゃなく耳だ!)。歌詞にある場面、言葉はさきほど劇で観たそのものだ。そうして矢野絢子の歌声とピアノを聴きながら、僕たちはふたたび劇の場面を思い出す。感動がじわじわとあふれてくる。この劇はこの曲を聴くことで完成するものだ。バラバラだったパーツ、不可解に残りつづけたものたちも、音色の中に溶けていく。
ミニライブが終わり、僕は余韻に浸りながら家に帰った。『八十五歳の女の子』をネットで買って聴いてみた。また劇の場面が浮かんでくる。歌詞の内容が染みこんできて、僕は笑った。「やや難解な戯曲」がこんなにもわかりやすく思えるなんて。
ここは地球ではないどこか別の星。これらのパーツの使い方が完璧にわかった。
「ゲキカン!」を書くのは今シーズンで3回目。2年目を迎える。演劇シーズン開催期間中に全公演の感想を書き上げるというミッションにビビるのは毎度のことだが、季節の祭りが今年もやってきたことが大変嬉しく、存分に楽しむつもりだ。しばらくは演劇の世界にどっぷり浸ろう。
皆さんを演劇の入口にご案内できるような「ゲキカン!」を目標に、拙文ながらも綴ってゆきたいと思う。
また、これから劇場へ足を運ぶ方の楽しみを奪うようなネタバレは避けるつもりだが、知らず知らず書いてしまっていることもあるかもしれない。ご了承いただければ幸い。
トップバッターは劇団コヨーテの「優しい乱暴」。観劇の前は戯曲に目を通しているのだが、この戯曲は1ページ目から既にただならぬものを感じていた。崖のギリギリ瀬戸際でふわふわと踊るような色気のある言葉の羅列に、どきりとした。戯曲に色気を感じたのは初めてだ。この舞台を先頭に持ってくるとは、今回の演劇シーズンはいつもと違う。攻めている。
舞台はバスの断面図のような風景の中、蟹江鳥生という男の独白から始まる。やがて女と男、蟹江の会話が繰り広げられるのだが、無邪気な子どもらが畳み掛ける言葉遊びをしているようで会話が噛み合わない。というか、支離滅裂。背景も人物も輪郭がなくて掴み所がない。まるで狂人の頭の中の会議を覗き見しているようで、観る側は戸惑うかもしれない。
その混乱の中でひときわ輝きを放つ、美しい詩のような言葉を響かせるのがこの物語のキーパーソンである85歳の女の子、原田摂子。三人はあらゆる場面で原田摂子に出会い、同じベンチに腰かけて会話する。このベンチのシーンは優しさに包まれる凪の時間で、救いを感じた。最後のシーンの原田摂子が響かせる詩は特に素晴らしい。(舞台を観終わったら是非戯曲もご覧ください)。
唐突に登場する頼りない殺し屋、待つ女、箪笥のこやしを作り続ける老婆。人間の可笑しさや残酷さが剥き出しになったキャラクターたちも魅力的だ。
あらゆる人間の現在と過去と未来、バラバラに見える各シーンが連なりやがてひとつの物語を紡ぎ出す。くすんだ色や歪んだ形、ひとつひとつはささやかな点の集まりで、離れて見れば、点の集まりが単色では作り出せない絶妙な色と模様になって表れる。そんな点描画を見ているような心持ちになった。「優しい乱暴」は作・演出の亀井健氏の純粋な心が描き出した芸術作品だ。
本編の後にはシンガーソングライター・矢野絢子さんのミニライブもある。豊潤であたたかみのある歌声が会場を包み、心が洗われるようだった。この舞台を作るきっかけになった曲だという「八十五歳の女の子」の歌詞の世界にも引き込まれた。よく映画館で字幕のあとすぐ席を立つ人がいるが、字幕のあとも重要なシーンがまだ残っていたりする。観客はライブという贅沢なお土産を受け取れるので、最後までお楽しみいただきたい。