

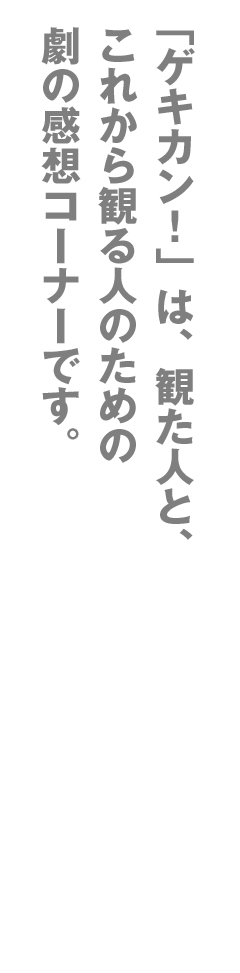

月刊「O.tone」編集長 平野 たまみさん
30年以上、タウン誌の編集に関わりながら、札幌という街を見続けてきた。1980年代当時は、日本が高度成長に支えられながら、後にバブルと言われる時代にひた走っていた頃だ。そういう時代は、大衆の間に様々な娯楽や文化が生まれる。映画、音楽、演劇、舞踏などなど、若者たちが旺盛な好奇心を次々に表現して、街は華やかな色彩に満ちていた。
演劇の世界で言うと、「駅裏8号倉庫」や「札幌本多劇場」が生まれ、様々な劇団が面白い芝居を発表していた時代だった。私もそんな芝居によく足を運んだが、1990年代に入ると、だんだん遠のいていく。小屋(=劇場)がどんどんなくなって、観劇できる環境が減ったせいもあるだろう。東京へ遊びに行くと、そういう場所がたくさんあって、心底、羨ましいと思ったものだ。
再び演劇を観るようになったのは、この「札幌演劇シーズン」の存在が大きい。
『西線11条のアリア』は、以前から気になりながらも見逃していた作品だ。2005年に東京で初演され、翌年には札幌でも開催された、斎藤歩さん(作・演出・音楽)の代表作といえよう。実在する電停「西線11条」の真冬を舞台に、物語は進む――。
この芝居は簡単に言うと、「フツーの人々が、フツーに生きて、死んだ」物語とでも言えばいいだろうか。生と死の境界線を、雪が吹きすさぶ「電停」としたことに全てが詰まっているように思う。時刻通りやって来る市電と、どこへ向かえばいいのか分からない人々。そこに、ススキノへ行こうとする東京から来たサラリーマンの横山さんが交差する。そして始まる最後の晩餐(正確には違うが…)。
始まりから観客を笑わせ、軽妙な台詞回しが心地よい。重いテーマながら、市電の魅力を披露する展開も面白い。東京のサラリーマンから見た「札幌の不思議な習慣」と思わせるマニアック?な会話。東京で初演したのもうなずける。
人はいつか死ぬ。
そしてそれぞれに、愛おしいフツーの人生がある。そんなことを、しみじみと考えさせられた芝居だった。
最後に、ご存じのように2015年春、市電がループ化され、「西4丁目」と「すすきの」が結ばれることになっている。
初演から10年。再演されることになったら、この物語はどう変化するのだろう。それもまた、楽しみである。
映画監督・CMディレクター 早川 渉さん
「演劇的。とは?」
2月8日、札幌市教育文化会館小ホール。「札幌演劇シーズン2014冬」の第3弾を飾る札幌座の「西線11条のアリア」初日の客席は、ほぼ満員の観客で埋め尽くされていた。シアターZOOという定員90席の小劇場を拠点にしている札幌座が、定員360席を有するこの大きな舞台でどのような芝居を見せてくれるのかとても楽しみだった。そして、約85分の芝居が終わりを告げたとき、観客からは割れんばかりの拍手!前から2列目で見ていた自分もまた、かなり長い間手を叩き続けていた。良い芝居だった。物語の詳細は他のページを参照していただくとして、ここでは今回の芝居がいかに「演劇的」であるかを確認しながら、その素晴らしさを伝えていくことにしよう。
じつは、今回の芝居を観る2日前、コンカリーニョで公演中の「言祝ぎ」(intro)のアフタートークゲストとして、作・演出のイトウワカナさんと対談をしたのだが、その席で「言祝ぎ」などの家族をテーマにした彼女の芝居の多くが実は「映画的」なので、今度ぜひ映画化させて!と勝手に盛り上がっていた。そして、今回「西線11条のアリア」を観た後に関係者の一人から「この芝居こそ映画にしやすいんじゃない?」と言われた。その時には「そうですね〜」とお茶を濁したのだが、心の中では「絶対に無理!!」と思っていた。
映画の世界では「一スジ、二ヌケ、三ドウサ」という言葉がある。要は良い映画を作るには、まずストーリー(スジ)、その次にカメラの技術(ヌケ)、そして役者の演技(ドウサ)を大事にしなさいと言うこと。ストーリーと役者の演技は映画特有のものではなく演劇でも共通するところだ。なので「映画的」なものを形作る要素としては「カメラの技術」が重要になってくる。では演劇はどうなのだろう?自分はここに「ライブ感」というキーワードを当てはめてみたい。この「ライブ感」というキーワードは別に目新しいものではなく、演劇の強みを語る上で必ず出てくる言葉である。実際、多くの劇団が「ライブ感」を強調するために生演奏を行ったり(今回の舞台でもあるが)、ダイナミックな役者の動きや演技を試みたりと様々な工夫を凝らしている。「西線11条のアリア」が素晴らしいのはこの「ライブ感」を生かす工夫が実に隅々にまで行き届いているところだ。劇中で雪を降らせ、地吹雪を起こすもじもじくんのような白いタイツを着た雪の精?たちは、この芝居が「作り物」であり、この場限りの夢物語であることを観客に告げている。電停の上で実際に時間をかけて炊きあげられるご飯は、劇中の時間が今観客が観ている時間とシンクロしたライブの時間であることを証明している。そして、広い空間を生かした繊細な照明と音響は、この場所に居合わせた者にしか体験できない「作り物」の美しさを存分に表現している。ここで、自分は気づく。「西線11条のアリア」を観てわき上がる感動の多くは、その場に居合わせた観客が見事に巻き込まれ、演出された「作り物」の世界にのめり込んだ結果なのだと。
この芝居を映画化することはもちろん可能だ。しかし、劇場で味わうことが出来た感動の半分も表現する事は出来ないだろう。ストーリーの良さ、役者の演技の素晴らしさを表現できても、観客と劇場空間を巻き込むことで発生するライブ感と感情を映画ではとうてい表現できない。映画は作り物のようでいて、実はリアルなモノ。演劇はリアルなモノに見えて実は作り物なのだ。
NHKディレクター 東山 充裕さん
このファンタジックな物語に流れる優しさはサッポロの夜の真実だ…。
舞台の冒頭、登場人物たちによって、穏やかなアリアが演奏される。その時から舞台と客席が穏やかな優しさに包まれる。
作品の色や匂いを決め、一つの世界を創り上げるのが演出家の最も重要な仕事である。
そしてそのために大きな役割を担うのが音楽である。(私が携わるテレビドラマやラジオドラマでは特にそうである)
演出家・斎藤歩の創る世界は、前作もそうであったが、心地よい優しさに溢れている。
物語そのものは、停車場で市電を待つ謎の年齢不詳の女性と、東京から来たサラリーマンとの噛み合わない会話から始まる。
その謎の女性を演じるのが林千賀子なのだが、実に不思議な女優である。彼女ならではの独特の間合いで、不思議美少女と不思議美魔女の間を行き来するのだ。一体どこに本音があるのかもわからない。それが計算なのか天然なのか…。
その独特な魅力にひかれ、私のドラマにも出演してもらったのだが、結局、彼女の正体はわからなかった。
今回、私がもっとも好きだったのが、停車場で皆がご飯を食べるシーンだ。
わけありの登場人物たちが、北海道の美味しい米を、北海道の美味しい水で炊き、子供時代から食べてきたような漬物やタラコや筋子などのおかずと一緒に食べる。皆、幸せそうである。
また、東京から来たサラリーマンを演じる彦素由幸のリアクションが良い。彼は『ダニーと紺碧の海』でも素晴らしい演技を披露してくれたが、彼の魅力の一つはリアクションにあるように思う。今や私は彼の大ファンだが、彼がご飯を食べた時は、本当に美味しそうで、思わずよだれが出た。
札幌市営交通の心づかいにも頭が下がる思いである。
観終わってからもなお、心地良い余韻がしばらく続く舞台だった。
ライター 岩﨑 真紀さん
息が詰まるような悲しみを抱えたとき、世界は限りなく美しくなる。空の青さ、降りしきる雪、見慣れた夜の道を照らす街灯でさえ、新しい輝きを帯びて胸に迫るだろう。
そして悲しみの中でなおも生きようとするとき、私たちは笑う。運命は残酷だけれども優しくて、生きるに足るだけのものを残してくれている、ということを確かめるように。
斎藤歩作・演出の『西線11条のアリア』は、地方色と笑いを織り交ぜた明るく楽しい旋律と、「人を見送る悲しみ」という普遍的な通奏低音による、葬送曲的な芝居だ。
この芝居で斎藤は、私たちを不用意に傷つけないよう、細心の注意を払ってくれている。冒頭の演出は、「どうぞリラックスして楽しんでください」というメッセージ。続く序盤では、登場する札幌の風物のあれこれのいじり方に、思わず手を打って笑わずにはいられない。でもふと気が付いたら、私たちは乗るはずだった市電に置き去りにされていて、斎藤が本当に見せたかった世界に向き合っているのだ。
気楽な序盤は落語でいう「枕」のようなもので、本編はここから始まる。
日常の風景の隣に、それがあることを私たちは知っている。普段は開けないふすまの向こうに、それはいつも鎮座しているのだ。私たちはそれを、できれば見つめずにいたい。
だから斎藤は、ふすまをほんの少し引いて、中に潜むものの気配だけを見せる。そして、それがあるからこその祈り、願い、夢を紡ぐ。
私たちは笑う。その笑いは、ふすまの向こうを想像してしまった自分をなだめてくれる。でも、笑いながら意識しているのだ、隣の部屋を。それはどんどん強くなり、苦しい心が笑いを求める。斎藤はちゃんと用意してくれていて、私たちはそれにすがるように笑う。笑う。笑う。精進落としの席で、あるいは葬儀からの帰り道で、故人のほほえましいエピソードを語り合っては笑う、あの感覚を思い出している。
人を失えば、私たちは悲しい。でも、そうだ、さよならだけが人生なのだ。
君はどこかに行ってしまった。どこへ、どうやって行ったのか。道連れがあってほしい。笑いがあってほしい。心残りがあっただろう、不運を恨みもしただろう。恐れに泣いた夜もあったかもしれない。でも、全てが終わった今はそれすらも遠く眺めて、どうかおいしいものを心ゆくまで味わったときの満ち足りた気持ちで、いつもの市電に乗るような気楽さで旅立ったのであってほしい。「世界は残酷だったけれど優しかった」と、ほほえみながら行ったと思わせてほしい。
これは、確たる宗教を持ち合わせない多くの日本人が抱く願いだ。人を失った斎藤の悲しみは、現代を生きる私たちに共通する無意識の祈りを、作品の中で描き出したのだ。
ラストで演奏される「西線11条のアリア」は、正しく挽歌であると同時に、斎藤の観客へのメッセージが込められているように思う。私には、こう言っているように聞こえたのだ。
「僕の悲しみを分かち合ってくれてありがとう」と。
編集者・ライター ドゥヴィーニュ仁央さん
食べることが大好きなあなたへ。
評判のお店のチェックはもちろん自炊でも手抜きなし、「今日は何を食べよう?」と考えることが勤務中の楽しみでもあるあなたに、ぜひ札幌座公演『西線11条のアリア』を見てほしいと思う。「食べることと観劇に、何の関係が?」と思うだろうけれど、まずは札幌市教育文化会館に向かってほしい。
冬の大通公園を横目に教文に到着したあなたは、入ってすぐ左手の小ホールに入る。目に飛び込んでくるのは、舞台上に静かに佇む市電の電停。パンフレットを読むと、どうやらそれは札幌に実在する電停らしい。
「今度沿線のお店に行くときは、市電に乗ってみようかな」とぼんやり考えていると、そこに会社員風の男が現れる。
東京から出張でやってきた彼が札幌の吹雪の威力を思い知る場面は、なかなかに痛快だ。「吹雪のことを誇らしく思ったのって初めてかも...」とおかしな気分で眺めていると、次々に人がやってくる。
でも、市電を待つ彼らは、何だか奇妙なのだ。
コンセントが付いている電停も変だけど、そこで米を炊き始める人たちはもっと変だ。
不思議なやり取りが交わされ、彼らの事情が判明していくにつれ、ホール内にご飯の炊けるいい匂いが漂い始める。
そして、彼らは最後の晩餐をいただく。電停に用意(!)されていたおかずとともに、とても美味しそうに。
帰り道、あなたはスーパーに寄って筋子やたらこを買うだろう。はやる心で台所に立ち、いつもより気持ちを込めて米をとぐはずだ。何百回も繰り返してきた行為なのに、この日は「ご飯が炊ける匂いって、なんて心が穏やかになるのだろう」なんてことを思ったりしている。
そして、丁寧にお椀によそい、「いただきます」と口にするとき、
あなたは、これまでその言葉を口にしてきた無数の人たちを意識するだろう。さっきまで自分の目の前にいた、彼らのような人たちを。
「普通の人が、普通に生きて、普通に死ぬ」。
ささやかに生まれては消えていった無数のいのちの連なりに、自分が接続したような感覚。
それは、本作に触れた人にもたらされるギフトだ。
私はあなたに、このギフトを受け取ってもらいたい。
あなたは、いつも一緒に美味しいものを食べ歩いている友人を誘って、期間中にもう一度見に行こうと思いつく。
「その前に、佐藤水産の飯寿司も買っておこう」。観劇後、絶対食べたくなるに決まっている友人がうらやましがるところを想像し、楽しい気分になったあなたは、お誘いメールを送る。
友人にも、あのギフトがもたらされるといいなと願いながら。
お客様の感想
あったかい涙が流れてきました。(30代男性)
舞台上で本当にごはんを炊いて、湯気が出てきたときには、びっくりしました。ほしのゆめ、京極の水、佐藤水産のいずし、たらこにスジコ、納豆に漬物…と、北海道に住んでいる幸せを象徴する食べ物でした。改めて自分が札幌に住んでいることに幸せを感じました。(無記名)
以前観たときと、同じように感じつつ、今だからこそ感じられることもあると思いました。 喪や供養ということは、残された側として必要なものですが、去るものにとっての納得するまでの時間ということについても、ゆっくり考えさせてもらえる芝居でした。(男性)
電停であの人たちに会ったらあたたかく見送りたいと思います。(40代女性)