


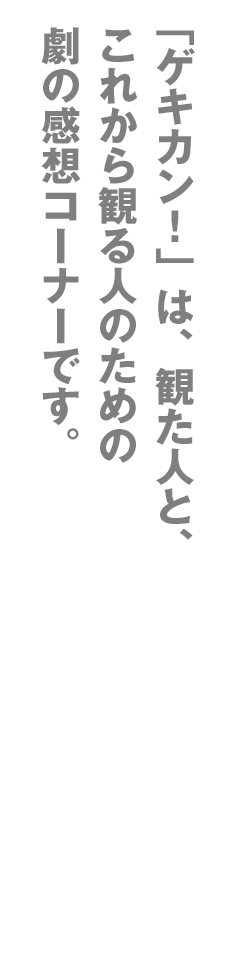

北海道大麻高校3年 赤坂 佳保さん
「風まかせ。」
コパフィールドの叔母と暮らすディックが、自作の凧を掲げて言った言葉だ。凧は風まかせに空を飛ぶ。どこへいくのかはわからない。風に吹かれて、上がったり下がったり。他の凧とくっついたり、離れたり。その姿は、様々な運命に晒された、デイヴィッド・コパフィールドと関わってきた人々、そしてコパフィールド自身の人生のように思えた。
人々は、ただただ一生懸命に生きていた。
いつも優しく見守ってくれた保母のペゴティは、愛する夫を失ってしまった。どんなにつらく貧しくとも、ミコーバー夫婦は笑顔を絶やさなかった。コパフィールドの妻ドーラは、若くして愛犬チップと共に命を落としてしまい、コパフィールドを育ててきた叔母のベッチーも破産してしまった。そしてたくさんの人との出会いと別れを繰り返してきたデイヴィッド・コパフィールドは、最後に大きな愛に気づき、アグニスと結ばれる。
皆決して希望だけではなく、困難ばかりだった。愛する人のため、守るべきもののため、社会の波にもまれながらも必死に生きていく姿が、生き生きと眩しく描かれていた。
他の凧とくっついたり、離れたり。糸が複雑に絡んだり、切れそうになったり。
いくつもの凧が、それぞれの風に吹かれて、強く、美しく空を飛んでいた。彼らが一斉に歌うシーンでは、舞台に風が吹いたようだった。彼らの帆がしっかりと風を受け止めて海へ出航していく姿からは、生きていくエネルギーが伝わってきた。
札幌山の手高校2年 仁木わかな さん
一人の男に明かりがあたり、「カメヤ演芸場物語」は始まる。昭和46年にタイムスリップしたかのように錯覚させる舞台。私たち高校生は「昭和」はわからないが、何だかどこか懐かしい感覚に陥った。細かい所まで「演芸場の楽屋」が再現されており、そこに置かれたモノを一つ一つ確かめるようにワクワクしながら見た。登場人物たちもとてもユニークであり、なおかつ少しクセがあり、笑いなしには見ることができなかった。
「楽屋」では、昭和の若者たちの追いかけている夢や悩み、それを包み込む昭和の年長者たちが、様々な出来事を繰り広げる。そして、学生運動にかける「夢」や漫才にかける「夢」。そんな楽屋に充満する「夢たち」に、その場にいるような感覚になった私たちは、胸を躍らせたり、息をひそめたり、ホロリと泣いたりする。
全身で芝居を感じることができるというのはこういうことかと強く感じた。芝居中で、「仲が悪いトリオ漫才師」の性格がきついリーダーが、やる気のないメンバーに「『たかがそんな夢』に命を賭けているんだよ!」と言う。私はこの台詞に強く心を打たれた。私にも「夢」があるが、他の人から見たら「たかがそんな夢」かもしれない。しかし、「たかがそんな夢に命を賭ける」ということは、なんてカッコいいことだろう。
この作品を観て「夢」というものを考えさせられた。私も「たかがそんな夢」に、「カメヤ演芸場物語」に出てきた人たちのように、思いっきり突き進んで行こうと強く感じた作品だった。
札幌山の手高校2年 佐々木 瑠那 さん
昔の浅草の、とあるお笑い劇場の裏舞台を描いた物語。最初の語りから引き込ませる世界観で、一人ひとりのお笑いに対する思い、そして人生の歩み方が強く熱く伝わってくる作品でした。現代の日本とは少し違うような、昭和の浅草、古き良きストーリーです。
「カメヤ演芸場」という演芸場に、一人の学生が指名手配され逃げてくる。いろいろな人と出会い、どんどんお笑いの世界に引き込まれていく一方、夢をみて共に戦ってきた仲間を裏切れない気持ちの中、お笑いコンビを結成する。今、自分のいる状況が楽しくてなかなか抜け出せず、沢山の仲間とぶつかり、夢を語り合い、笑ったり、時に泣いたり、すれ違ったり。様々な人間模様を見ることができました。
私が特に感動したのは、夫が飲んだくれである夫婦漫才師の妻が病気になったシーン。夫は酒を止め、また妻と漫才することを願う。しかし、無情にも妻の容態は悪くなる。夫の願いは「また妻と舞台に立ちたい」。妻の願いは「夫が新しい相方と舞台に立ってほしい」。すれ違うお互いの思い。妻が後輩の女芸人に「自分はもうすぐ死ぬから、私が生きている間に夫の新しい相方になってあげてちょうだい」と頼む。夫婦の過ごしてきた時間の厚みが描かれ、ラストに強い感動が生まれたように感じます。
浅草芸人が生きてきた世界観、それに私は深く陶酔し、この作品に人間が追い求めるものの真の姿が描かれているのではないのか、と気づかされたような気がします。
札幌山の手高校2年 篠原 拓海さん
小劇場は、その名の通り広くなく、席数も少なく、もちろん芝居をするエリアも小さい。しかし、大きなホールよりも身近に芝居の空気を感じることができる。作り手が届けたい緊張感や狂気がとてもよく感じられる。今回の『木に花咲く』は、その芝居の中の「空気」が痛いほどに伝わってきた。自分が普段の部活動で使用するのは、学校のステージか大会のホールなので、小劇場で演じてみたいなと思った。
実を言うと、この芝居についての事前情報は一切なく、一体どんな芝居になるのだろう、と考えながら開演時間を迎えた。開演前のアナウンスが流れただけで、何となくだがこの芝居の重い空気をわずかながらに感じた。そして始まり、老婆が花見をしながら意味深な台詞を言う。桜の木、花びらに美しさを感じた。
この芝居の主軸となる家族は家庭崩壊を迎えており、息子(老婆の孫)は情緒不安定であった。そして老婆は孫のよき理解者であろうとするがために、その愛がある種の暴走を引き起こしてしまっている。家族が崩れる、という話は現代もある話だが、なにか現代的ではない雰囲気を感じる。おそらく設定はどの時代であってもいいのだろうが、電話のベル音や、携帯電話がでてこない点、男1(よしお)が手書きで日記をつけていること、小学生のときの服装から見るに昭和期の、特に1980年代を意識しているのではないだろうか、と思った。老婆は気が強く思い込みも激しい。だが、孫にたいする愛情は計り知れない。それがはたして男1にとって良いことなのか、親子関係は修復されるのか、と観ていたのだが、とてつもなく悲しい最後だった。最後までだれも報われず、かつ救いようのない事件の連続。その空しさ、夫婦のやるせなさ、男1のもはや止まる気配のない暴走、すべてが本当に目の前でおきているかのように生々しく舞台から客席全体に伝わってきた。役者たちの迫真の演技と、先に触れた小劇場の利点が相まって、自分には心が痛くなるほどこの家庭の深刻さが伝わった。自分の家族とは全く違う家庭とはいえ、何かの拍子でこんな風に壊れてしまうかもしれないと思ったし、家族に対してなにかしらの複雑な考えや感情を抱いている方が観たら、きっと登場人物の誰かに自分を重ね合わせてしまうかもしれないだろう。
観劇後知ったことなのだが、やはり三十数年ほど前の実際の事件からヒントを得た作品であった。愛のかたち、親への憎しみなど、普段考えることのない話がたくさんつまっている作品なので、この芝居を観劇することは、「家族」ついて考える、刺激的なきっかけになるのではないかと思う。
札幌山の手高校2年 仁木 わかなさん
最初舞台にはセットが置かれていなかった。「どうやって展開していくのだろう」と期待を胸に、芝居が始まるのを待っていた。3人に明かりが当たる。ひざまづく小汚い青年、軸がしっかりしていそうな女、人がよさそうな男、彼が男と女に何かを頼んでいるところから芝居が始まる。そして回想シーンになり、セットは役者が持ってきて、その場その場でどんどん形を変えていく。
作品のタイトルでもある「デイヴィッド・コパフィールド」とは一人の男の名前である。彼の幼少期、青年期、壮年期を2時間ちょっとで一気に観ることができた。ディテールにこだわりぬいた家具や小道具からは、雰囲気やにおいまでもが感じられ、映画を舞台で観ているような、まるで19世紀のイギリスの世界に入ったかのような感覚になる。
彼の半生はとてもいい人生とは言えない。むしろ、不幸な人生を送っていた。だが不幸の中にも幸福があり、幸福になったと思えば不幸になる。自分にも分かる感覚であり、観ている人もきっと少し「共感」を覚えたのではないだろうか。少なくとも私は共感した。
この芝居は「彼」だけの話ではない。幸福や不幸を繰り返しながら、それを意識したりあるいはとらえきれないままに、それぞれの人生を歩んでいった「彼の周りにいる人々」の話でもあると率直に思った。
今を生きている私たちもそうではないだろうか。自分だけが人生を歩んでいるのではなく、自分の周りもそれぞれの人生を歩んでいる。その中で人に出会い、恋をしたり、憎んだり、悲しんだり、腹を抱えて笑ったり。そんな日々を過ごしながら「今」を人々は生きている。「人生」は人が生きて死ぬことであり、長いようで短い。そんな「人生」を不幸ながらも、すべてを引き受け引き寄せ、必死に生き抜いていった「デヴィット・コパフィールド」の姿は、私に「今」を生きる勇気をくれた。
札幌山の手高校2年 佐々木 瑠那さん
開演ギリギリに劇場に着く。舞台セットは、中央に大きな桜の木と、その前に花見用の敷物、その右隣にドア。私が今までにあまり見たことのないシンプルさであり、そしてそれがどんな場所なのか、広がりをもって提示するセットである。真っ暗な客席に和を感じさせる音が流れ、緊張感の高まる中、舞台に明かりがつく。一人の老婆が花見をしながら酒を飲んでいる。
物語はちょっと昔の家庭問題の話。夫を亡くした老婆とその孫、そしてその両親は、庭に大きな満開の桜の木がある一軒屋で暮らしていた。老婆は淡々としゃべり始め、舞台に桜の花びらが舞っていく。一気に物語に引き込まれる。
物語の中盤のある日、孫が家の中で包丁を持って暴れる(世に言う家庭内暴力である)。少年は、家から暴れて飛び出すが、庭の老婆に持っていた包丁を渡す。このシーンのとてつもない緊張感が印象的だった。家族はどんな悲しみ、痛み、辛さがあったのだろうと思うと、自身の家族観は常に揺さぶられ、私は涙が止まらなかった。
老婆は人を憎むことを孫に教える、「悔しい気持ちを忘れるな」と語る。孫はその老婆の話、言うことを聞く。
それをあまり良くは思わない両親。この「負の感情の取り扱い」を巡っては、様々な視点から見ることができる芝居であると感じた。私は「様々な視点から見ることができる」と解釈したが、この解釈すら見るものによって意見が変わるだろう。そんな芝居。
悲劇的な最後。それに直面する家族。「満開の桜の木の下には死骸が埋まっている」という、芝居の中で既に亡くなっていた老婆の夫が、生き姿で出てきたとき、何度も口にした言葉。全てが終わった後に舞台に流れた曲もまた、私の涙を止めさせてはくれなかった。
観劇のあとで知ったことだが、この物語は本当にあった事件などにヒントを得たらしい。そのことも、劇場を出た後の私の心を揺さぶる。
クラーク記念国際高校3年 太田茉菜 さん
「ピンチの時こそチャンスあり!!」
会場に入り一番に目に飛び込んできたのは、壁に貼られたその言葉だ。客が日頃見ることのない芸人達の楽屋がそこにはあった。
時は昭和46年。もちろん私は生まれていないし、その時代を生きていない。なんとなく聞いたことのある歌、ギャグ、なんとなくでしか知らないその空気をとても身近に感じた。師匠、若手、裏方、とそれぞれの立場があるが、家族のようにも見えた。楽屋という家の中で、悩み苦しむ子の話しを聞き、人生経験を語る親。家のような温かさがあった。
そして何より驚かされたのが役者のアドリブ力だ。私は「カメヤ演芸場物語」を二度観劇したのだが、一度目と二度目では全く違う。同じ演技をするのはもちろん不可能だが、客をグッと引き込み笑わせる技術が凄まじい。言葉ひとつにしろ動きひとつにしろ、その場で生きている人間として笑いを生むその演技力とアドリブ力に脱帽する。生でこの空気に触れているからこそ、手をたたき、声を出して笑えるのだ。
物事には必ず終わりが来る。そう感じる舞台であった。笑っていたかと思えばじんわり切なくなり、泣けてきてしまう。師匠たちの言葉を、楽屋のイスに座りじっと聞いている、そんな感覚になった。
人はなぜ舞台に立つのか、それはそこに客がいるからなのだろう。笑わせ方や闘い方はそれぞれ違えど、皆胸を張って生きている。芸人も、その裏で支える者も。
若い、という絶好の世代で私は何をしようか、と考え込んでしまった。そんなことを考えていることが「若さ」なのかもしれない。
北海道大麻高校3年 赤坂 佳保さん
最高の舞台になった時、客の拍手と笑い声で会場がうねる。そんな舞台を目指して夢を追い続けるカメヤ演芸場の人々。汗も涙も流しながら、夢に向かって突っ走る彼らの姿に、強く感銘を受けた。
舞台は昭和の浅草にあるカメヤ演芸場。細部まで作りこまれた楽屋と路地裏、懐かしい音楽、「浅草キッド」。会場に入った瞬間、高校生の私でさえも笑ってしまうほど昭和の香りを感じた。そして個性が強い、いや、個性がキツイぐらいのキャラクターを演じていた役者たちのパワフルな演技に圧倒され、すぐに舞台の世界へと引き込まれた。
学生運動に参加し、一斉検挙の中でカメヤ演芸場に逃げ込んだ水口は、演芸場の人々が夢を必死で追い続ける姿に次第に惹かれていく。トリオ漫才師の石崎が相方達に「漫才に命懸けてんだよ!」と言い放つシーンは、痛々しくも共感を覚えた。夫婦漫才師ロマンカレンのカレンは、大病を患い、「ロマンカレン」襲名披露の日、会場がうねるような拍手と笑い声を聞きながら、息を引き取る。すれ違いながらもお互いを想う二人の深い愛情は、切なくも美しかった。
想いが強い分、時には声を荒げて傷つけてしまうこともある。必死になってもどうにもならないこともある。それでも最高の舞台にするという夢は同じだから、傷つけても傷つけられても、支え合って一緒に頑張れる。そんな彼らを、あたたかい昭和の演芸場が支えていた。
漫才に人生を懸けた彼らの姿と、演劇に高校三年間をかけた自分と自分の仲間たちの姿を重ね、何とも言えない気持ちが涙とともにあふれ出てきた。この作品は再演だと知り、もう少し時が経ってから、もう一度この作品を見てみたいと感じた。つたないながらも最高の舞台を目指した高校での大切な日々を思い出し、今とは違う感動を得られる気がする。
言葉にならないほどの感動をくれた“カメヤ演芸場物語”に、「客の拍手が、笑いの渦が、まだ聞こえる。まだ鳴りやまぬ…。」
札幌山の手高校2年 仁木 わかなさん
桜の木、ゴザ、少し傾いた扉。芝居が始まる前から見入ってしまう、何だか不思議な空間が、私の目の前に広がっていた。作品を観(み)終わったあと私は「?」―このマークが頭に浮かんだ。分からなかったわけではないが、分かったわけでもない。この気持ちを言葉にするのはとても難しいが、一つ挙げるなら「もどかしい」。
老婆になついている孫の少年。しかし老婆は彼に厳しい教育を施す中で、「憎しみを忘れるな」と言い続ける。両親との関係もあまりうまくいってない様子であり、成長した少年は精神的にまいってしまう。そして老婆との関係もその極みを迎える…。
時代設定は、30年ほど前の日本だと思うが、このような悲劇は、今の社会でも起こっていることである。そのような時代を超えた切迫性が、この芝居には十分盛り込まれている。私がこの作品中で目を追って見てしまうのは、やはり少年であった。特に印象に残っているのは、春になると出てくるアリを殺しながら(老婆は割り箸で、少年は素手で)会話をするシーン。私はなんだか不気味、いや、背筋がピンと伸びるような感覚に陥った。少年がアリを殺しながら何を思ったのか、何を想像していたのか全く見当がつかない。しかしその「見当のつかなさ」が、当然私が経験したことのない「人を殺す前の気持ち」として、逆にリアルさを醸し出した。
そんな重いテーマだが、重いだけではなく、どこか切なくはかない。そして「もどかしい」。こう思わせるのは、きっと老婆の後ろにある一本の桜の木のせいではないか。照明によって、昼間の桜や夜桜になったり、青色の暗転で現れる桜の影がとても幻想的だった。それは、近いけど遠い、一定だけど一定ではない、まるで「家族」のような。普段家族に囲まれて過ごす私すら、いまだ意識したことのない感覚をこの芝居で体験し、業の深さを間近で観ることができた。
(本劇評は2月5日の北海道新聞夕刊文化面に掲載されました)
札幌山の手高校2年 篠原 拓海さん
劇団イナダ組の芝居は何度か観(み)たし、イナダさんには部活動に指導に来ていただき、演出や芝居についての貴重なお話を聞かせていただいた。一番印象に残っているのは「芝居の作り手がメッセージ性なんて求めるな」という話。とても驚いた。イナダさんいわく「テーマやメッセージは台本にあって、役者や演出がその通りにやったら説教臭いものになる。最初のテーマはどんどん薄まって、お客さんになにか伝わるものがあればいいのだ」。
今回の「カメヤ演芸場物語」を観終わったとき、この話を思い出した。役者たちは舞台上ですごいエネルギーを発し、高い演技力を存分に披露した。「学生運動」「1971年(昭和46年)」「浅草の芸人」という、北海道に住み、その時代を知らない自分でさえ、素直に「いい芝居を観た」という気持ちになった。
誰が主人公、と聞かれたら、僕はこの舞台となっている「演芸場」だと思う。支配人の代が変わり、あれやこれやとしている間に夫婦漫才師のけんかに楽屋はめちゃくちゃ、さらに舞台の進行役を務めるジロウが、妹の学生運動の同志と漫才コンビを組むことになったり…と、登場人物みんながまんべんなく活動し続け、静かになることはほとんどない。テーマやメッセージ性より、そこにその人物が「生きて」いて、彼らの芸に対する思い、自分はどうすべきか、などいろんな思いが入り交じる。そんなドラマが繰り広げられ、人物が精神的に成長する舞台となり、登場する芸人たちに愛されている「演芸場」こそ主人公ではないか。
役者のアドリブなのか演出なのか、その時代には絶対ないはずの「ウォークマンを聴いている人」の動きなど、小ネタも取りそろえている。「ありえないだろ!」と笑って突っ込んでしまいそうなところも、何の違和感なく他のシーンと同じ色で見せてしまうところに演者の実力の高さを感じた。ノスタルジーにとらわれることなく、全く芝居を観たことがない人も心から楽しめる作品だと思った。
(本劇評は2月5日の北海道新聞夕刊文化面に掲載されました)
北海道大麻高校1年 櫻庭 柚月さん
「愛と死」
この劇を観終わって私は愛と死は切り離せないものだと感じた。この芝居の中には、たくさんの愛と死が溢れていた。
デイヴィッドの最愛の母は、再婚した夫とその姉から精神的なストレスを受けて体を壊して亡くなる。デイヴィットの親友のスティアフォースはデイヴィッドの幼馴染であるエミリーと駆け落ちするが、その後死んでしまう。幼少期からデイヴィッドのお世話をしてくれていた保母のペゴティも夫を失ってしまう。そして、デイヴィッドも妻のドーラを亡くしてしまう。これらの死の背景にはすべて愛が存在している。失う愛、誕生する愛。無くなる想い、生まれる想い。舞台上で、そういうものが交差していった。最後にデイヴィッドは青年期にお世話になったウィックフィールドの娘であるアグニスと結ばれる。アグニスはずっとデイヴィッドのことを見守り、支えてくれた姉のような存在である。デイヴィッドがアグニスへの想いに気がついたのはドーラを亡くした悲しみを持ちながら出た旅の中だ。デイヴィッドは旅を経てアグニスへの最大の愛へたどり着くことができたのだ。デイヴィッドの乗り越えてきた様々な死が最後の愛へとつながっていたのだと思う。
デイヴィッド・コパフィールドの原作はとても長いものだと聞いた。それを凝縮させて、デイヴィッドの人生にある愛と死についてまとめた脚本は素晴らしいものだ。演出面でも、デイヴィッドの人生の様々な場面を切り合わせた脚本を無理なく進めることができたのは効果的な舞台転換があったからだろう。工夫された舞台転換はスムーズに劇をすすめ、観客はずっと「デイヴィッド・コパフィールド」の世界に浸かっていられた。私は人の人生を表した劇を見るのは初めてだったが、心の中に温かいものが残るそんな劇だった。
北海道大麻高校1年 櫻庭 柚月さん
この舞台はとてもテンポがよかった。芝居の全編を通してスピード感があったが、見せるべきところはテンポを落とし、観客に、人は誰でも色々なセカイで戦っているということを伝えていた。
この劇では舞台美術が展開の良さに貢献していた。舞台セットはカメヤ演芸場の楽屋と楽屋を出たところの道路の二つが設置されていた。道路で演技をしている人たちがいたら、中でサイレントの演技をしている役者がいた。それは道路のシーンを別のシーンとして扱うのではなく、楽屋のシーンとのつながりを表していた。
そして役者の演技力の高さも劇のテンポを支えているもののひとつだった。テンポが良くスピード感があったからこそセリフ回しが早いところがいくつかあったが、役者の滑舌がよくしっかりと聞き取ることができた。重ねて何人もの役者が様々な話題をしている時も、声の声量や演出の仕方で観客に聞いて欲しいセリフが分かるようになっていた。キャストの掛け合いもスピード感があったが、観客を置いていくことは無く、しっかりと観客を意識した劇だった。例えば観客の受けが良ければアドリブでセリフを入れたり、観客が笑ったところは何度もおもしろおかしく繰り返して同じシーンをやっていた。スピーディーな展開で笑いをとるところ、十分に沈黙で使い笑いをとるところなど色々なテンポで観客を引き込んでいった。そして引き込んでいった観客をそのままラストに連れて行った。ラストのシーンは、今までのテンポがあるからこそ落ち着いたゆっくりとしたテンポが活き、観客は引き込まれたままだった。こんなにも観いってしまう劇があるのかと、終わった瞬間、言葉に表せない感動が私の中に押し寄せてきた。緻密に計算されているようで、されていないような全てアドリブなのではないかと思わせてしまうぐらいのテンポで本当に観ている人を魅了した作品であった。
北海道大麻高校3年 赤坂 佳保さん
この作品は、単なる不条理劇ではない。「家族と社会」という問題への悲しい叫びである。爆音で鳴り響くその叫び声は、私の耳と胸を痛くさせたが、絶対に耳を塞いではならないと感じた。
舞台には満開の桜の木が一本。桜は照明の色によって様々な表情を見せる。その根元で老婆が酒を飲み、仲に亀裂のある娘夫婦と、いじめにあっているという孫へ、静かに、時に激しく訴える。
ある日、孫のヨシオは学校へ行っていないことを隠して老婆を訪ね、アリを殺すのを手伝う。一つ一つ丁寧に潰しても、何度もわいてくるアリを見て、家を飛び出してしまう。憎しみの絶えない現実に耐えられなかったのだろう。不気味な雰囲気の中で、ヨシオの弱い心を社会が蝕んでいる様子がはっきりと描かれていた。
ヨシオがクラスメートの送別会に一人だけ呼ばれなかった時、父親はヨシオを仲間に入れてもらおうとする。父親は「軽蔑されても構わない」と言うが、老婆は「おまえがそう言うからヨシオは憎み方がわからないのだ」と止める。憎みたいのに、相手にされない。ヨシオの心にたまった憎しみは、親へ刃を向け、最後には自分にも刃を向けてしまった。“無関心”は子供の心に追い打ちをかける、どれほど恐ろしいものかを考えさせられた。
老婆はヨシオに、「憎しみを忘れるな。」と言った。老婆はヨシオを、胸いっぱいに抱えた憎しみを何か別の大きなものに変えて、美しく咲く桜にしてあげようとしていたのだ。老婆の底知れない深い愛情でさえも、家族と社会の闇には勝てなかったのだ。ラストの降り積もる桜の花びらは、老婆の涙のようで、私の心に重くのしかかった。
社会が子供の心を蝕み、家族がそれに追い打ちをかける。そうしてたまった憎しみが、家族を傷つける。今多発しているこの社会問題への激しい批判。目をそらさずに、きちんと向き合うことが、見たものの責任であると感じた。
北海道大麻高校1年 櫻庭 柚月さん
この劇には本当に圧倒された。まずはダンスだ。いくつのダンスが組み込まれているのだろうと思うぐらい多く、ローザが違う国に行くたびに、その国の国旗を持って踊る人や、その国のダンスを踊ったりしていた。さらに舞台転換に使っていたり、どれも迫力のあるダンスばかりだった。次に驚いたのは表現方法の多様さだ。長いセリフを言う時に他の役者がそのセリフに合わせて水牛の演技や、手紙の内容などを表現していて、目で見て分かる芝居をしていた。音響を使わないでドアをノックする音や開ける音、風の音、列車の汽笛や走る音などを人の声で表現していることがすごいと思った。
最初は葬儀のシーンから始まり、四人の女性がお墓の前で色々な話をしていた。その四人の女性が17歳から47歳のローザを演じている事に気付いたときの衝撃は大きかった。この劇では同じ役者がいろいろな場面で様々な役を演じていた。それを何事もなくやってしまう演技力は素晴らしかった。ラストの近くに四人のローザが集まり、会話をするシーンは、17歳から47歳のローザがユダヤ人として差別に対し革命のため勇敢にたたかい、民衆を愛した思いを感じた。最後の役者が歌うシーンは本当に感動的だった。その歌は最初の葬儀に歌われていたものでもあり、最初のシーンから一つにつながったと思った。
舞台は1800年後半から1900年前半にかけてのヨーロッパの差別や革命の状況を知ることが出来るものだった。当時の人達は苦しみながら闘い、勇敢に生きていた。この作品は自分の思ってることはしっかりと口に出すことの大切さについて伝えているのだろうか。私の生きている時代からは、全く想像のつかない世界。しかしこの芝居の一端から、私は確かに感じることができた。真っ赤に染まるラストは本当に感動的で美しく、目に焼きつくようなシーンであった。
クラーク記念国際高校3年 伊沢僚二さん
劇場に入るとそこには一本の桜が舞台中央に聳え立っていた。観劇前はどこか桜のセットが幻想的で美しく見えたが、観劇後の桜はとても残酷で無情なように見えた。下手側に設置された扉は不自然に傾いていた。一方で役者たちの演技は非常にナチュラルだった。だからこそあえて不自然な扉だったのだろうか。特別な意味合いがあるように思えた。
この作品を楽しんで見る人はそうはいないかもしれない。寧ろ楽しまれてしまっては、この不条理演劇は成立しない気がする。この作品を見終えた人は恐らく人間の持つ黒い感情に対する恐怖か、あるいは味気ない虚無感に駆られるはずだ。「腑に落ちない」「納得のいかない」そんなモヤモヤを舞台上に残していった劇団新劇場の皆さんに見事と言いたい。
家族関係における殺人のニュースを聞くたびに、私は憤りを感じてならない。しかし、この不条理演劇には心苦しいが共感してしまう部分もあった。不謹慎ではあるが、殺人衝動というのをどこか身近にあるものだと感じた。そして何より、この舞台において少年が自らの命を絶つその心理とは如何なるものだったのだろうか。自殺の理由として「楽になりたい」と聞くこともあるが、同じ世代として、特に若者の自殺は空しい。舞台の上の少年はもう誰も憎むことがなくていいようにと自らを殺めてしまった。「人の死」がすべての問題の解決になるのだろうか。そうでしか終われないものがあるのだろうか。そんなことを考えさせられた。
私も役者として「いじめ」や「人の死」に関する作品を取り組んだ時がある。しかしその時とは違い、この作品を見終えた私はとても不快で不可解な気分になった。だがこれこそ不条理演劇の美しい醜さであり、魅力である。愛・憎しみ・無関心など人間の心理が描かれたこの作品を私は忘れることはないだろう。これからの人生を生きる上でこの演劇を通して訴えられた言葉にし難いメッセージを、心のどこか片隅に留めておきたい。
クラーク記念国際高校3年 横山真友子さん
ぐるぐる、がやがや。
目に入ってくるのは、そんな動き。
耳に入ってくるのは、そんな声達。
コパフィールドの心とは真逆な、
騒がしい街並みを役者たちが見事に表現していた。
気を抜いたら、その雑踏に紛れてしまいそうな…
『デイヴィット・コパフィールド』は舞台の魅せ方が特徴的だと思った。役者が大道具をぐるぐると回転させることで、観客の目線は変えられていく。ちょっと向きを変えれば、いろんな役者の顔が見える。「おおっ」と思わず心でつぶやいてしまった。知っている役者さんが多い舞台だったのだが、今まで「この役者さんは、こういう演技をする」と勝手に思っていたのだが、今回は全く違った。「そんな一面があったのか」と、役者さん一人ひとりが持っている演技の幅に驚いた。
これまで他の舞台を見たときは、役者さんが一人で何役もこなしているのを見て、「さっきあの役やっていた人だ」と感じていたが、デイヴィット・コパフィールドではほとんど感じなかった。その中で私が最後までそう感じなかったのは、石川哲也さんが演じる二役だった。その二役が石川さんという一人の役者によるものだと全く気づかなかった。舞台が終わりを迎える頃にやっと、「ああ、お父さんは、バーキスだったの!」と気がついた。
いつも見ている役者さんのいつもと違う顔を見せてくれた『デイヴィット・コパフィールド』、その物語を見ている私の顔も、いつもと違ったのかもしれない。
クラーク記念国際高校3年 横山真友子さん
会場に入ると、真っ先に目に飛び込んできたのは、いつもみるサンピアザとは違う、客席を飲み込んだ舞台。開演すると、その飲み込まれた客席のように、私も舞台に飲み込まれていった。
ローザ・ルクセンブルク。
私はその人物も、その時代も知らない。
物語についていけるだろうかと不安になり、役者のセリフを聴くことに神経を注ごうとしたその瞬間、すぐに耳に入ってきたのは音楽だった。
楽器とともになる、声。
声とともに観る、動き。
その一瞬一瞬放たれる役者の動きと音色が、まるで舞台が生きていて、心臓を脈打っているように感じたのだ。
ドクン、ドクン、と。
ああ、この舞台は観るんじゃない、
聴いて感じることのできる舞台だ、と思った。
千年王國さんの舞台を初めて見た私にとって、橋口さんの演出は型破りのようなものだった。
体という楽器をフルに使い、セリフや歌で音色を聴かせる。
なんて魅力的なんだろう、と。
見終えた後には、まるでコンサートを聴いていたかのような熱が、私の胸の中にあった。
北海道大麻高校1年 櫻庭 柚月さん
この作品はとてもメッセージ性の強い劇だ。きっと、誰の心にも響いただろう。特に老婆の語る言葉が印象的だった。
「花も命のもの。狂ってどうしようもなく咲く。命ってのは春になると狂うのさ」
これは老婆が自分の娘に語りかける言葉。私は「狂う」という言葉を今までは恐ろしい意味でとらえていたが、ここでは恐ろしい中の美しさを意味している。満開の櫻はとても美しいが、その分吸い込まれそうな恐怖もある。花にも命があり、花が満開になるのは命が狂ったように咲くからである。狂ったように咲いた櫻は人に美しさや恐怖を与える。そして静かに櫻の木の下で繰り広げられる物語も美しさや恐怖を秘めていたのだろう。
老婆の愛する孫であるヨシオは小さい頃からいじめの標的になることが多く、それは高校に入っても変わることはなかった。そしてヨシオは学校に行かず、家で両親に暴力をふるうようになる。そんなヨシオに対して老婆は「人を憎め」と何度も言う。自分をいじめる奴ら、そして父親を。「優しさ」とは何か。「憎しみ」とは何か。「愛する」とは何か。ヨシオや両親は老婆の言葉によって深く考えていく。しかし、最後にヨシオは自殺という結果を出してしまう。ヨシオは老婆のセリフを受けてどういう思いで自殺をしたのか。そして両親や老婆はヨシオの死を体感して何を感じたのか。ヨシオの受けたいじめ、両親へ暴力ふるった記憶を辿りながら考えることができるだろう。
私はヨシオの頭をなでながら様々なことを語る老婆を見て自然と涙が流れた。目の前に咲き誇る櫻の美しさ、そして頭の中に流れ込んできて、まるで私自身に語りかけているような老婆のセリフに強く心打たれたからだ。この作品はぜひとも、私と同じ世代、ヨシオと同じ世代に観てもらいたい。メッセージ性の強い劇だからこそ、心の中にある思春期ならではの自分ではコントロールできない苛立ちのもどかしさを老婆やヨシオが代弁してくれるだろう。そして、自分やヨシオとは違う立場の両親の心情も感じることで自分の両親への思いや自分に対する思いも変わってくるのではないかと思う。
クラーク記念国際高校3年 伊沢 僚二さん
これが札幌座の演劇か。
パワフルでエネルギッシュな演技が織り成す展開に笑わされてばかりだった。畳み掛けるような会話でスピーディに物語を進める役者たち、その滑舌や集中力、そして客席までも舞台にしたダイナミックな演出は飽きを感じさせることがなかった。私も役者として演劇に取り組む際、演出家に「もっと畳み掛けるように」と要求されたことがある。これが中々、一筋縄ではいかない。それをやるには自分自身の技術もそうだが、共演者への信頼も欠くことができない。芝居が共演者に気を遣ったものになった途端、消極的で不自然な芝居になってしまうことが何度もあった。しかしこの札幌座の舞台上はまさに共演者同士が互いにぶつかり合い、畳み掛けるような会話が、それぞれ削りあっていくように重なっていった。そんな緊張感をはらみながら、確実にストーリーは組み上がっていった。圧巻だった。
この作品は日本人と韓国人によって繰り広げられるお話だ。言葉の通じない人同士で、一つの作品を作り上げている。この作品は演劇に秘められた可能性を見せてくれたのかもしれない。これからも演劇を通じて多くの異文化間交流が行われることを切に願う。今まさに世界は異文化の衝突の最中にある。しかしその一方で、日本の地方都市札幌の小さな劇場で僅か数人の役者が、言語の次元を超えて観る人を笑わせている。自分の世界が広がっていく可能性を感じさせてくれる。それだけでは不十分であろうか。国と国が分かり合うにはこれだけでは足りないだろうか。いやもう私たちは分かり合えている。こう感じられる機会がここにありましたと多くの人たちに伝えたい。札幌座はこの後何を見せてくれるのだろか。楽しみでならない。演劇というツールを通じて北海道を元気にしてほしい。そしてそれが、世界の演劇を盛り上げる先駆けになったらと思う。演劇を通じて、1人でも多くの人が国を越えて繋がれるように。
北海道大麻高校3年 赤坂 佳保さん
韓国。
なんだか理解し難い隣の国。未だ解決しない領土問題、メディアから伝えられる反日感情ばかりをイメージしてしまう。だが、舞台の上で韓国人と日本人がワイワイと一尾の蟹を楽しそうに食べる様子を見て、「案外上手くやっていける相手なのかもなあ。」と感じた。
舞台はススキノにある中華料理店。使い込まれた、味のある店のあたたかい雰囲気。暖簾のかかった戸は、店の中と外を巧みに表していた。日本語と韓国語の台詞が飛び交ったり、字幕をわざと劇中に登場させていて、言葉の壁がむしろ面白かった。アルバイトの韓国人、ソングが玉ねぎを炒め、開演前から客の興味を引く。
店主のヨシコが、近くに越してきた韓国人のスジョンへ、隣人の三郎のことを「変な人だから、あまり関わらないほうがいい」と伝える。だが、ソングが店に届いた活タラバガニを逃がし、大騒ぎになっているところへ変人の三郎が茹でた蟹を持ってふらっと現れ、関わらざるを得ない状況に…。「不思議なものは不思議なままがいい」と蟹を手に入れた経緯をなかなか話さなかったが、確かにそれは逃げた蟹だった。変わり果てた姿となった蟹は、もうどうすることもできず、全員で食べることにする。
理解のできない相手と進んで関わりたいなんて思う人はそうそういないだろう。しかし、一つの食卓を囲んで蟹を食べる彼らは違った。理解できないから関わらないという考えはなく、互いの個性を認めて歩み寄っていた。近づけば近づくほど見えてくる不思議な部分も、「面白いじゃない。」と笑いながら受け入れる。それぞれの素朴な疑問に共感し、笑いがこみ上げてきた。
蟹を通して、二つの国が握手した瞬間を目にしたような気分だった。
中華料理店から漂うおいしそうなカレーの香りを感じながら、海の向こうに横たわる少し近寄り難かった隣人と、「気軽に立ち話ができる関係になれたらいいなぁ」なんて思う。
北海道大麻高校3年 赤坂 佳保さん
観(み)終わってすぐ頭に浮かんだのは「生もの」という言葉だ。生身の人間から生きた言葉、歌、動き、感情が発せられる。楽器も生演奏。そして、実際に19〜20世紀のヨーロッパを生きたローザ・ルクセンブルクの人生をまぶしく描く。生々しく、生き生きとしたエネルギーが、会場全体をいっぱいに満たしていた。
19世紀のヨーロッパの香りがする舞台セットは、ドイツ、イタリア、ロシアなどのどの国にも見える。序盤の効果音は人の声を使っていたが、状況がひどくなるに連れて冷たい鉄の音が響くようになる。いくつもの黒い椅子はさまざまな物に変化し、目まぐるしく移り変わるローザの生きた時と場を創造していく。舞台だけでなく客席からも役者が飛び出す。舞台転換のスピードと迫力ある役者の動きは、会場を巻き込み、終始、客の目を引き付けた。
「勇気を出し、あきらめることなく、そしてほほ笑みながら―どんなことがあろうとも」。夢を見つめ、優しくほほ笑みながら私たちに語る。社会主義運動家のローザは、どんな逆境にも決して屈さず、民衆の心に寄り添う。常に希望を持ち続ける強さと優しさにあふれた姿は、空を自由に飛び回る鳥のようだった。自由を手に入れるため、社会や政治と命懸けで戦い続けていたが、最後は軍人たちに暗殺されてしまう。
歌、踊り、演技のハーモニーで、そんな彼女が舞台の上にしっかりと立っていた。彼らが歌い、踊れば、「風」が舞台から吹いてくる。その風はきっと、ローザという希望の鳥を、自由に力強く飛ばせるためのものだったろう。
生身の人間が全力で歌い、踊り、心の底から叫ぶからこそ発生するパワーでなければ、今もなお人々に激しく訴えかけてくるたくましいローザの姿を描き切ることはできなかった。血の通った役者たちがローザ・ルクセンブルクに命を吹き込む。その光景が、たまらなく私の心をつかんだ。
(本劇評は2月23日の北海道新聞夕刊文化面に掲載されました)
北海道大麻高校1年 櫻庭 柚月さん
この劇は1匹の蟹(かに)をめぐる日常から日韓問題へ展開していく内容だった。
日本と韓国は隣国でありながら遠い国だ。言葉ひとつ取ってもそうだ。字幕がスクリーンに映し出されていたが、私はハングルは一つも読めなかった。しかし劇中で日本人と韓国人は言語の壁を乗り越え、時には体全体を使い、身ぶり手ぶりで交流を図っていた。互いの国をどう思っているのか、また韓国人2人の日本に対する思いの違いなどが語られていた。その会話を受けて、韓国を少し怖いと思っていた私は、同様に日本を怖いと思っている韓国人もいることに気づいた。今まであまり考える機会がなかった韓国との関係を考えることができた。
脚本には伏線になるようなせりふが多く含まれている。しっかりと解決される伏線もあれば、伏線のように聞こえても最後になっても解決されないものもあった。例えば中華食堂のオーナー・よしこさんが共に店を開いた夫と離婚した理由や、韓国から留学している女子学生が東京からなぜ札幌のススキノへ引っ越してきたのかなど。いつ解決するのか、観(み)ている間はまるで喉に棘(とげ)が引っかかっているような感じだった。だが、観終わった後は、せりふや演出の深い意味まで推測した。「本当はこうだったのだろうか」「あのせりふはこういう意味だったのだろうか」とさまざまな考えを巡らせた。舞台で起こることや伏線が、全て解決しないからこそ、深く考えさせるのだろう。
日常から切り抜いたような物語は、劇が終わってもまだまだ続くように感じられた。単にみんなが幸せになって終わるのではない。登場人物はこれからも生き続けていく。問題はこの先も簡単に解決されることはなく、それは現実の日韓問題にも繫(つな)がっている。作品を通して感じたことを、これからも考えていかなければならないと思った。
(本劇評は2月24日の北海道新聞夕刊文化面に掲載されました)
札幌山の手高校2年 佐々木 瑠那さん
客席で同伴者と会話していると、客電(照明)も落ちないまま、いきなり青年が出てきて舞台の上でタマネギを刻み始める。芝居が進むにつれ、徐々に彼が韓国人であることが分かってくる。寒い季節。札幌・ススキノの中華食堂で働く韓国人青年と、大学留学のため札幌に来た韓国人の女性、その周りの人たちの日常を描いた芝居である。
芝居の鍵となるのは、タイトルにもある「蟹(かに)」。何らかの手違いで、店に届いたのは発泡スチロールに生きたままで入っている蟹。その蟹を青年が逃がしてしまい、周りの人たちはさぁどうする…といった、実にコミカルな内容だ。そして言葉やしぐさなど、国を越えて生じる「違い」というものを最大限に生かした舞台であった。
劇中で2人の韓国人は韓国語でも会話し、訳が字幕としてモニターに映される。その使い方もスマートで、斬新さを感じた。照明の演出として、暗転し切る直前に、蟹だけをライトアップする趣向があった。ただそれだけだったが、蟹と蟹に関わる人のおかしみが倍加された気がして、印象的だった。スープカレーを食べるシーンでは、小さな劇場に香りが漂い、ふだん芝居を観(み)るときに使わない感覚も刺激され、さらに親近感・共感がわく。忘れられない演出が多かった。
蟹は韓国語で「게(ケ)」という。「蟹」は「게」である、と観客が理解し、さらに「蟹」と「게」の境界があいまいになるにつれ、私はますます舞台にひきつけられ、目が離せなくなった。韓国と日本ではもちろん食べ物も文化も言葉も違う。呼ばれ方やとらえ方の違う「蟹(게)」。しかし、実体は同じモノ。
いま世間を騒がせる「日韓関係」を思う。文化や言葉や歴史観の違いを背景として起きた争いも、同じ希望と同じ落としどころを欲しているのではないか。私がこの芝居を観て「蟹」と「게」の国境を超えたように、日韓の争いもなくなる日も来るのだろうか。
(本劇評は2月24日の北海道新聞夕刊文化面に掲載されました)