


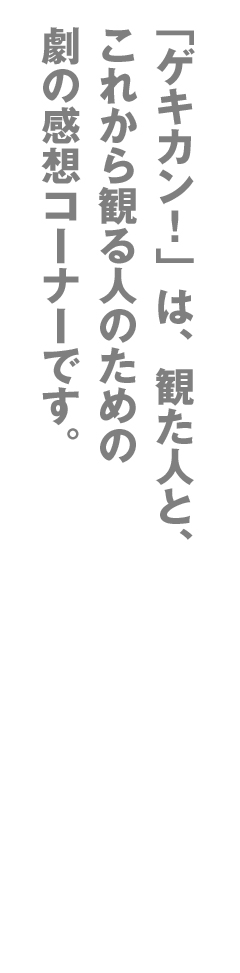

映画監督・CMディレクター 早川 渉さん
「ノスタルジックに潜む切なさとは?」
平成27年1月22日夜。琴似の劇場コンカリーニョ。
「カメヤ演劇場物語」の初日を観に来た観客でぎっしりの館内は、笑いと涙がたっぷりの昭和人情喜劇に大いに沸いていた。自分も観客の一人としてとても楽しんだ。この原稿を今晩中に仕上げ無くてはならないのでとっとと帰路についたが、本当は知り合いと琴似の焼鳥屋あたりで一杯引っかけながら今回の芝居について大いに語りたかった。見終わった後にいろんなコトを語りたくなる作品は間違いなく良い作品だ。今は仕方がないので、劇中で夫婦漫才師の片割れロマンが飲んでいたウイスキー「ニッカ ブラック」をちびちび飲みながらこの原稿を書いている。
昨年公開された日本映画に「青天の霹靂」という作品がある。
監督はピン芸人の劇団ひとり。主演は、おなじみ道民のアイドル大泉洋。
ストーリーは、売れないマジシャンの晴夫(大泉洋)が突然昭和48年の浅草にタイムスリップしてしまい、当時芸人をしていた若き父とコンビを組んで舞台に上がる・・・という少しファンタジーっぽい人情話だ。
あまり期待しないで観に行ったのだが、なかなか面白い映画だった。ストーリーそのものも良いが、何よりも昭和48年当時の浅草の雰囲気、芸人たちの雰囲気を良く表現している。映画としてのリアリティーが良くできている映画だった。「劇団ひとり、やるじゃん!」と観終わったとき思ったものだ。
今回の「カメヤ演芸場物語」とも少し重なる符号を持つ映画でもある。
昭和48年の浅草が舞台ということ。そして大泉洋という役者が拘わっているということ。「カメヤ演芸場物語」初演時に大泉洋はロマン役で舞台に立っている。
映画「青天の霹靂」の見所が映画ならではの映像表現で昭和の浅草、芸人のリアリティーを見せているところだとすれば、「カメヤ演芸場物語」の見所は、舞台の上でピチピチと跳ね回る、まさに水を得た魚のように生き生きと演じる役者たちの躍動感だ。舞台に上がっている役者は誰一人として無駄な役者はいない。無駄な役柄はない。皆が役をちゃんと生きている。この芝居は楽しく、そして少し切ない・・・
「青天の霹靂」は主役である大泉洋演じる晴夫と父・劇団ひとりの和解のストーリーであり、昭和から平成という繋がっていなさそうで繋がっている時代感を家族の絆を通して描いている。
「カメヤ演芸場物語」は昭和というファンタジー空間で生きる芸人たちの群像劇だ。そして、ここに描かれるのはどこかノスタルジックな世界観で、今に通じるリアルな感覚はほとんど無い。昭和は完全に過去だ。
完全な過去。
かつてそこにあった何かピカピカしたもの。
この芝居に感じる「切なさ」とは、そういうことなのかな。
帰りの夜道、昭和の浅草とは何の繋がりも感じない札幌の雪道を踏みしめながら思った。
在札幌米国総領事館職員 寺下ヤス子さん
いやいやいやいや、おもしろいお芝居見せてもらいました。会話構成、めっちゃ、楽しかった。これ、舞台は浅草ちゅことやけど、なにわ版も作ってくれへんかなあ。
人生の「闘い」て何なんやろ、今、私は闘ってるんか? 何と闘ってるんや?て考えさせられました。イナダ組は初めて観るし、「北海道ルール」という本に大泉洋は北海道の英雄、と書いてあったけど、その彼がいた劇団なんやと初めて知った。よそ者全開。
さて、もしカメヤ演芸場の支配人がドラッカーの「マネジメント」を読んだら。共通の目標設定は、観客数を増やす。個々の芸人の個性を理解し、長所を伸ばす。観客のニーズを知り、人気のない芸人は削減する。というようなことになるかも知れない。しかし、そんなもの、取るに足らない算段だったろう。カメヤ演芸場を、その日笑いのどよめきとなりやまぬ拍手で包んだのは、人情だった。そして支配人はその強いリーダーシップを、ガンと一発警官を気絶させることで、見事に全員に知らしめたのだった。ここ一番というときに盾となって責任をとってくれる上司。憧れます。劇場経営にはマイナスだったけど。法や経営よりずっと大事な人の道。人情はドラッカーを超えるのだ。それを裏打ちするのは、芸人魂、Show Must Go On のプロフェッショナリズム。何が彼らをプロにするか。彼らの心意気に他ならない。
登場人物が個性豊かで分りやすかった。透明感があっていいなと思える俳優さんもいた。
こういう「いいな」感やあるいは「それってどうよ」感は、この出来事を間近に観ないと味わえない。役者さんと観客の化学反応もあれば、観客同士、どこからか聞こえるすすり泣きに安心することもある。作者が予期しない感動が、個々の観客に生まれているかも知れない。ロマン・カレン夫妻、じろうや羽子板、学生運動、トリオ決裂、とネタは多い。今夜の出来事は、二度と体験できない。同じ芝居でも毎回何か違うから。きっと体験しておいたほうがいい。
もう一歩、仲間と感想を語り合う、あるいは一方的に語る、のも実にいい。
ドラッカーが、コミュニケーションとはについて語った章に、無人の山中で木が倒れたとき、音はするか、という質問があった。答えはノーだ。誰も聞かなければ音はない。音波は発生しても、誰かが音を耳にしない限り、音はしない。音は知覚されることによって、音となる。
誰にも話さなかったら、感動がなかったことになるわけではないが、誰かと共有すると楽しい、かも。(個人差があります。相手にもよります。) 演劇シーズンも、ツイッターやフェースブックで意見募集中だそうなので、宣伝してみた。
ライター 岩﨑 真紀さん
良い意味で、悔しい作品だった。ベタな笑いと人情は、本来、あまり得意ではない。なのにうかうかと面白がってしまったからだ。
舞台はじょろじょろガチャガチャ、といった感じで始まったのに台詞も間合いも早く、序盤ではその後を心配してしまった(観たのは二日目だ)。けれど、まずは腹話術の人形(人間が演じる)が出てきたあたりでうっかり笑い、酔っ払い漫才師とそれを追う妻が駆け込んできたあたりで「おお?」と思い、ジロウが淡々と語り始めたあたりから、芝居の呼吸に取り込まれた。非常に達者に作られた舞台だ。そのまま賑やかに進むのかと思いきや、お笑いトリオのトラブルから急転直下のハートフル路線に突入したときは、ちょっと驚いたけれど。
正直に申し上げて、あまり集中して見たとはいいがたい(こちらのコンディションの問題もあり)。聞き逃した台詞もある。でも大丈夫、余計な小細工のないこの作品は、観客をけして置き去りにしないのだ。聞かせどころのセリフはきっちり入ってきたし、カレン姐さんが想いを託す場面など、泣かせどころではしっかり共感させられた。時代設定が飛び回るお笑いネタも、あれ笑っちゃったよ、という感じ。
うん、本来の「芝居見物」はこういうもの、という気がする。気楽に観て、雑多な要素の中の自分が理解できるところで笑って、決めどころでちょっとシリアスな気分になり、最後はほんわりと人情を味わって。「時代の課題が…」とか「演劇とは…」なんて、大抵の人にとってはどうでもいいことだ。演劇作品を人に勧めるときは趣味嗜好を考えてしまうものだけど、『カメヤ演芸場物語』なら、近所のおばちゃんにも勧められる。
私が一番好感を持ったのは、自分が抱えているものと「がっぷり四つ」にならないジロウの存在だった。学生運動に疑問を感じたあげく、演芸場の進行係に。だからと言って人生を投げているわけでもなく、流れがくれば舞台で一勝負。妹や仲間を案じつつ、無理強いも、身の丈に合わない手助けもしない(が、要所では手を貸す)。
下手に演じたら嘘くさくなりそうなこの役柄を、ごく自然に演じた藤村忠寿に脱帽。本人がこういう方なのではないか、と思わされたほどだ。
浅草っぽくないなぁとか(早川監督同様、私も映画『晴天の霹靂』と比較連想していた)、演芸場にしてはいかがわしくないなぁとか、みんな真っ当な人に見えるなぁとか、そんなことも感じはしたのだけれど、野暮の骨頂、細けぇこたぁいいんだよ。
などと書きつつも、一つだけ。ラスト、逃げた学生運動家が戻ってきたシーンは、私にとっては蛇足だった。あの場面のおかげで、亀谷演芸場という世界を完結させていたメルヘンの魔法が冷めて、「指名手配されているのなら逃げ切れるはずもない、彼の今後の人生はどうなるんだ」などと心配してしまった。いい夢を見て終わりたかったのに。
ドラマラヴァ― しのぴーさん
その夜、日本から何千キロも離れた国では、日本中、いや世界中が息を潜めて命のやりとりの行方を固唾をのんで見守っていたし、創成川の向こうでは先日幕開けしたばかりの有名なミュージカルを楽しんでいた人々もいたでしょう。そこから、昭和46年という、僕のようなロートルを除けば、ほとんど有史以前のような時代へタイムスリップしたのが、この「カメヤ演芸場物語」です。昭和46年と言えば、ニクソンショックが起こり、沖縄返還協定が締結され、NHKが総合放送での全番組のカラー化を実施した年です。アイドルという言葉が生まれたのも、この昭和46年と言われています。時代背景には、泥沼化していたベトナム戦争にアメリカが破れ、学生運動も一部の過激派、具体的には連合赤軍が、翌年あさま山荘事件を起こしてその残忍さに世間が震撼した、そんな昭和なお話です。
「デイヴィッド・コパフィールド」のゲキカンでも書きましたが、僕はドラマプロデューサーというまったく右も左も分からない世界にいきなり放り込まれて、半ば強制的に演劇という表現と出逢いました。初体験は、札幌座と名前が変わったTPS(シアタープロジェクトサッポロ)です。今や個性派の実力俳優として活躍する斎藤歩が、まだ東京へ行けない時代でした。その次に出逢ったのが、当時一際輝いていたのが、イナダ率いる「イナダ組」です。「組」なんて、あなた、今時、土建屋やヤクザか、映画やドラマでしか使いませんよ。どれも、怪しい業界ですよね。この演劇シーズンのパンフレットに2004年の初演時の写真が載っていますが、みんな若い。大泉洋という北海道が生んだ奇跡のスターは、決して水曜どうでしょうという番組から出たのではなく、このイナダ組から生まれた俳優だと、僕は今でも思っています。それだけ、この「カメヤ演芸場物語」はイナダの代表傑作であり、この飲んだくれの夫婦漫才歴22年という設定のロマン役は大泉洋のアタリ役でした。ちなみに、物語の主軸の一翼を担う支配人はTEAM NACSのリーダー、森崎博之が演じていましたし、この劇の本当の主人公、秋田徹郎を演じていたのが、同じくTEAM NACSの音尾琢真でした。まさに、札幌から錚々たる役者を輩出した名作とも言えるでしょう。
イナダの代表作のスラップスティックコメディらしく、ドタバタあり、ギャグあり、そして裏を走っていた伏線が大見得を切り、物語がそこから一気にギアチェンジして人情とホロリとする涙あり、最後は大団円を迎え、そこで終演かと思いきや、劇の本当の主人公に寄り添って、青春の蹉跌というほろ苦い余韻を残して終わる。実にウェルメイドで安心して最後まで楽しめます。でも、2015年に再演する意味は僕には別物だと思うのです。
こんな温かな場所や人間の関係性はもうないのです。もう「カメヤ」が描くような世界はどこにもない。でも、こういう本当に小さな世界かもしれないけれど、たかが人生じゃないか、と安心して居られる場所があったらいいねよ、というノスタルジックな幻想だと提示してくれることに意味があるのだと思うのです。
「木に花咲く」のゲキカンでも書きましたが、小屋に入った時に、舞台の立て込みは是非気にされた方が良いと思います。僕のドラマドクターである岩松了はこう言っています。「劇はいつも舞台の中央で起こってるわけじゃない」と。またこうも言っています。「台詞を謳うやつが主役じゃないんだ」。さすがは、師匠のおっしゃる通りです。「カメヤ」の劇は、実は舞台中央に豪華に立て込まれた演芸ホールの楽屋ではなく、その舞台下手にある、街灯がたった一つ灯る路地で起きているのです。布石はすべてこの暗い路地で打たれています。トリオザザスカイラインも、惚けた落語家も、下手な手品師も、ロマン(初演時に大泉洋が演じていました)とカレンの夫婦漫才師というどうしようもないダメダメな群像は、突然、演芸場に逃げ込んできた一人の”革命家”のための、良い意味で騒がしい引き立て役です。そして、隠されている本流を観客に手引きし、表舞台へとひっぱり上げるのが藤村忠寿演じる進行係のジロウです。かなり、劇作的には暴力的ですが、やがてネタバレ状態で演じられる「ピンチとチャンス」という漫才コンビの有り様こそ、この劇の核心です。涙を誘う、イナダ組の看板女優、山村素絵演じるカレンとロマン(ツルオカ)の涙の別れ。余命短く逝った二代目カレン襲名披露の初舞台というハレの場に、お約束事として踏み込んで来る公安の刑事たち。これ以上は書きませんが、やはり、イナダ。手練です。
イナダは、ずっと札幌の演劇シーンを引っ張って来ました。劇団と言わず、「組」というプロデュース公演の形をとってきたのも、自分のスタイルを頑なに守りたいからだと思います。イナダ組のお芝居には、大きなハズレはありません。でも、僕はイナダ組の「オセロ」や、イナダ組の「ゴドーを待ちながら」も観たいと思う。劇作家であり演出家であるイナダは、芝居の出来映えは当たり前に必要。しかし、その出来映えとは全く真逆なところで商業性も成り立たねば、演劇は、少なくとも札幌では成り立たないことも知っている人です。まだまだ、独りよがりの”劇団”も少なくない札幌の演劇シーンの中で、イナダは自らが面白と信じる劇作を続け、芝居を目指す無謀な後輩たちに背中を見せながら、生き残って来ました。僕には、ずっと変わらない芝居を作り続けることで、時代に抗ってみせたような気がしています。
その意味で、藤村忠寿というトーシローを起用したことに何かの意味を見いだしたいと思うのです。僕の同僚でもある藤村についてここで説明する必要はないでしょう。藤村は、あのTEAM NACS相手に「蟹頭十郎太」(原作は嬉野雅道が書き下ろし、僕が芝居台本の形にしたものを、最終的に藤村が戯曲にしました)という伝説のテント芝居で舞台演出を手がけ、スペシャルドラマの監督も3本撮った、ただのサラリーマンのおっさんだけれども、一人の表現者として舞台に上がったはずです。「大俳優になった大泉洋がもう札幌で舞台に立てないのであれば、一緒に盛り上げていこうよ。そのためなら、おれは舞台に立つよ」、みたいなことをイナダにいったに違いないと僕は思います。そうやって、芝居を観ることの閾値が下がれば、札幌の演劇界にとってお芝居好きの裾野が広がることにつながるかも知れません。そのことに藤村が貢献できるのであれば、どんどん使い倒してやって欲しいとも思います。
ですが、こうも思います。藤村忠寿に寄せてしまったように見えるのは、決して好ましいことではないと思います。端々に、いわゆる楽屋落ちの台詞もありました。観客サービス、なのでしょうけれども、それは演劇の有り様としては違わないでしょうか。多分、藤村は穴の開くほど台本を読み込んで、この裏主役を演じたはずです。台詞回しは決して巧いとは言えないし、劇が自分に起こっていないときに、まったく動けてはいません。一緒に企むのであれば、人寄せパンダではなく、一人の役者として厳しく育てて欲しいと願うのです。それと、藤村忠寿という男はとても人間力溢れるやつですが、「劇薬」です。取り扱いには十分気遣ってやって下さいね。今夜、僕は藤村を観ていて、彼の抱える暗いものを見てしまったような気がしているからです。最後に、俳優、藤村忠寿のお話になって申し訳ありませんでした。ただ、この部分のゲキカンは僕にしか書けないと思うので。よい子の皆さんは、ゆめゆめ、藤村見たさにコンカリーニョに行かないように。
やっぱり、イナダ組はいい。イナダ組に呼ばれる役者はいい。そして、札幌にイナダ組がいて良かった。
NHKディレクター 東山 充裕さん
わかりやすくてライトな人情喜劇です。
さすがイナダ組という感じで、的確に計算された構成で物語が進みます。
また出演者たちそれぞれの芸の技量も高く、楽しませてくれます。
2004年の初演では、大泉洋、森崎博之、音尾琢真ら「TEAM NACS」の面々が出演されていたそうです。今回とは全然違うものだったのかもしれません。
この舞台は、役者たちによって大きく変わると思います。
役者たちが漫才師や落語家、学生運動家にどこまでなりきれるかが勝負です。
漫才や落語や学生運動に、真剣に人生を賭けている姿を、それぞれの役者がどう見せてくれるのか…。
場面によっては、芸人だけが持ちうる凄みを見せることも必要でしょう。
ラストシーンが少々意外でした。
演出家が意図しているかどうかは別として、それまで積み上げてきた世界をひっくり返しているようにも見えたからです。
今回描かれている演芸場の世界はファンタジーです。芸を志す人の真剣さや覚悟よりも、そこに集う芸人たちの温かな人情味に重点を置いて描かれています。
ところが最後に、漫才師として人気を博した学生が再び運動家に戻るというとは、その演芸場で過ごしてきた生き方を否定し、人は心地よい温かな世界に生きるのではなく、現実と闘うべきだと言っているように思えたのです。
もし演芸場の世界が真剣勝負の場として見えたなら、芸人たちの生き様に影響を受けて、学生運動に戻ったという解釈も出来たと思います。
ただそれには、今回の演芸場はあまりにベタな人情喜劇でした。
逆にその分、学生運動に戻った彼が、見えない闇に向かって走っていく後ろ姿が、いつまでも頭の中に残るラストでした。